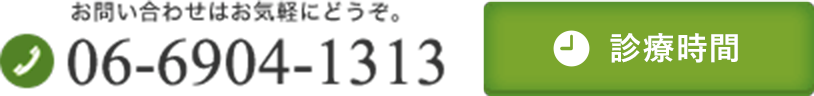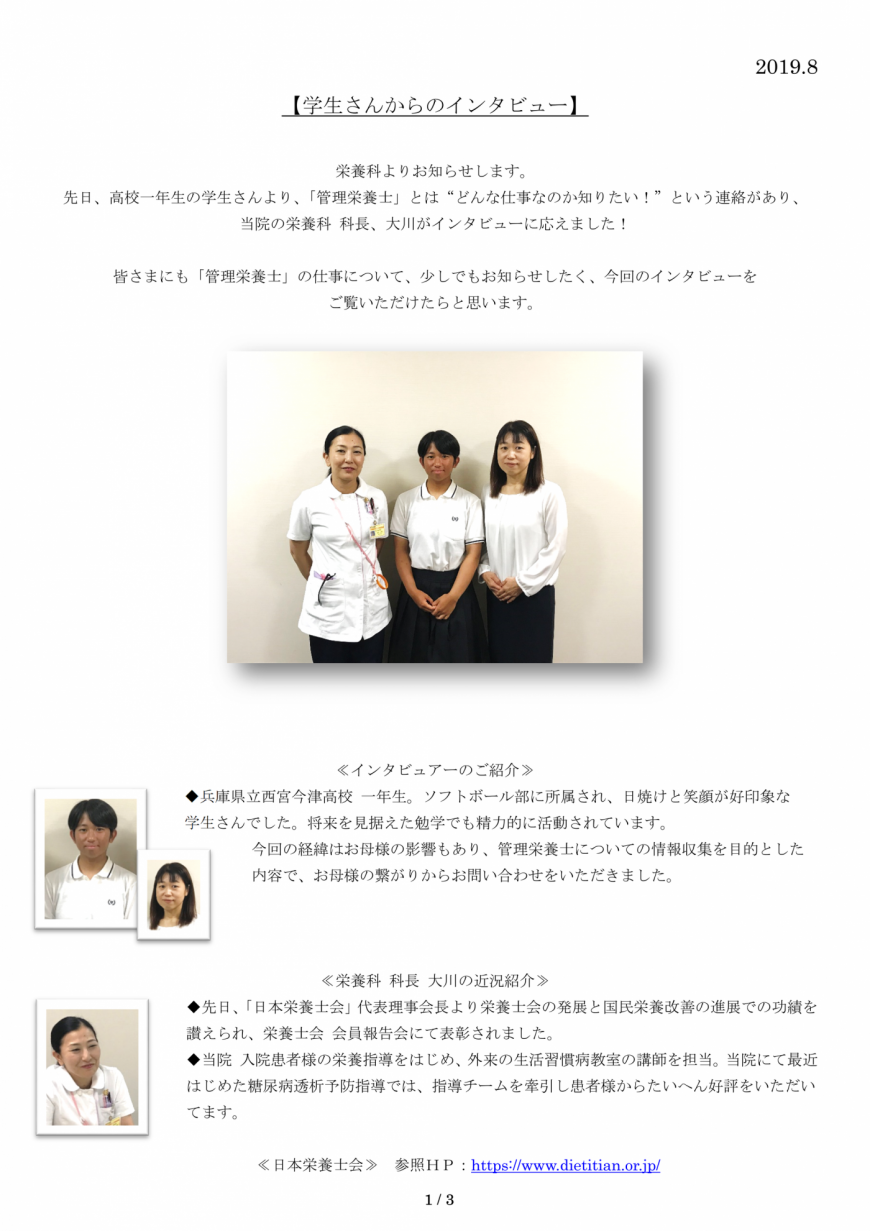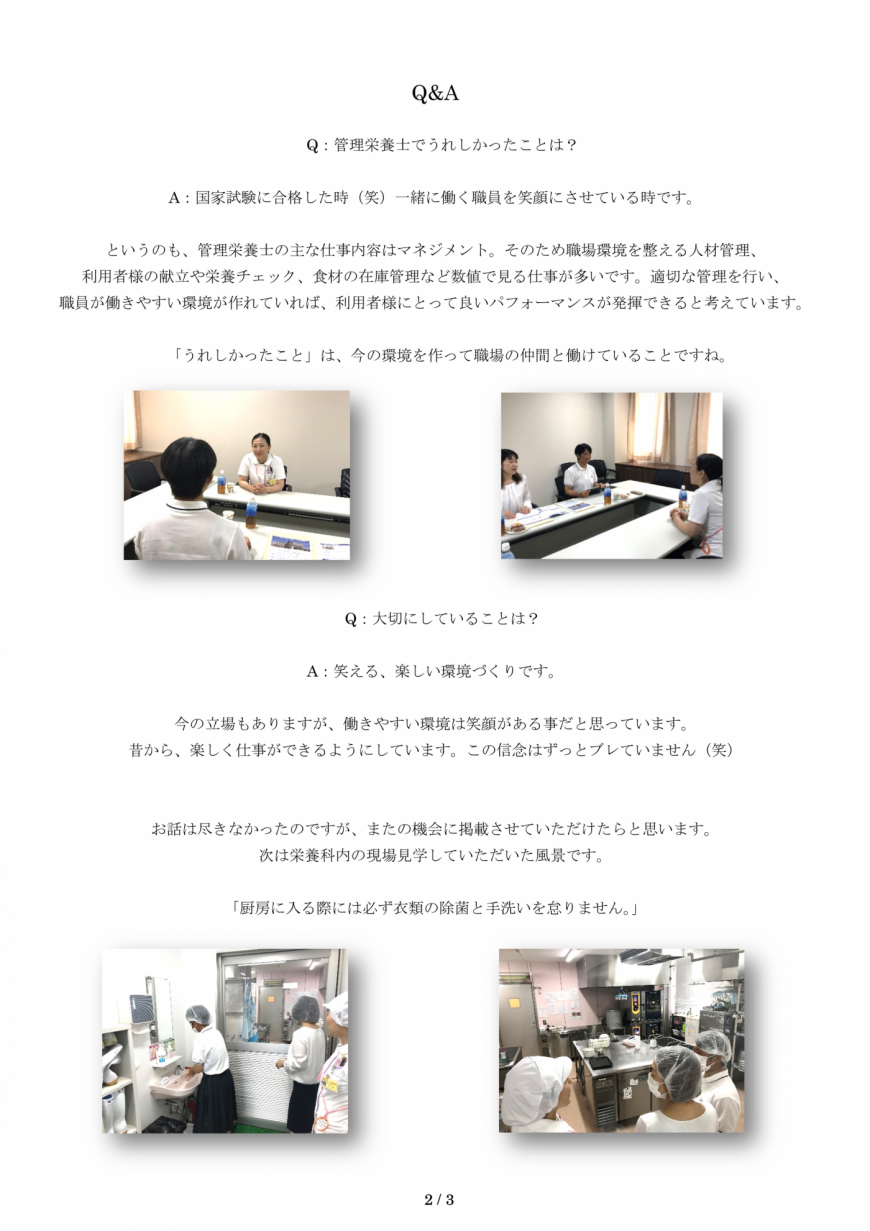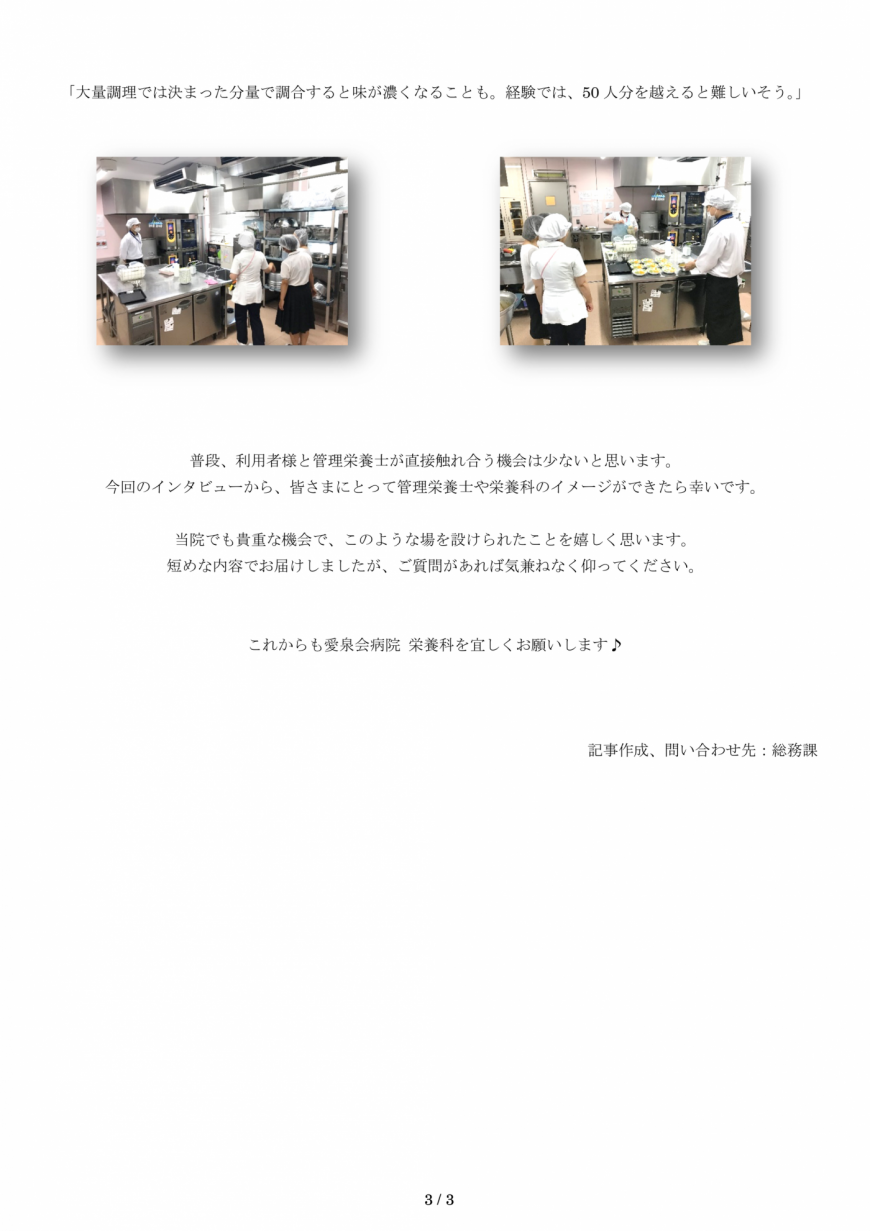栄養科
栄養科

入院患者様の一日も早い健康の回復を常に考え、
医師の指示のもと各患者様に適したお食事を提供しております。
直営の厨房で調理しており、美味しいと喜んでもらえるように
天然の鰹と昆布で出汁をとり調理しております。
当院には摂食、嚥下訓練を目的に入院している患者様も多数おられ、言語聴覚士や看護師とも連携し、各段階に応じた形態で提供しており、年13回の行事食も実施しています。
入院患者様の食事以外にデイケア利用者様の食事・院内保育所の食事も提供しています。
その他に入院及び外来患者の栄養指導、
外来での糖尿病透析予防指導(月10件)
生活習慣病教室の開催(年10回)
そしてNST稼働に向けて準備を行っています。
食事時間及び種類
食事時間 朝食: 8:00~ 一般食:常食・軟菜(全粥・7分粥・5分粥・3分粥)・流動食
昼食:12:00~ 高血圧食 経腸栄養
夕食:18:00~ 特別食:糖尿食・肝臓食・腎臓食・心臓食・膵臓食・脂質異常食
胃潰瘍食・貧血食・検査食・その他